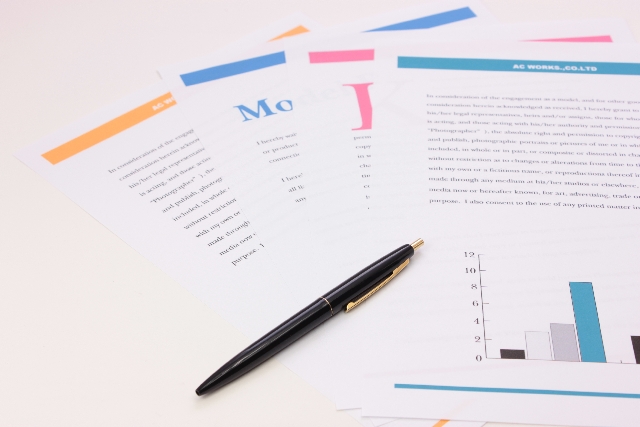


結婚退職について
6月に結婚するにあたって、先日3月末で退職したい旨上司に告げました。すると昨日、2月から会社は新しい体制に入るからできれば3月中にやめてほしいといわれました。
まだ新卒で入社して1年目です。1年働いたら失業保険はもらえると思うんですが、この場合1年未満になってしまうので失業保険給付の対象にはならなくなってしまいますか?
自分としてはやめたかった会社なので、結婚というやめる機会ができたことで良かったんですが、(実際3月末までいるのは、もう仕事のあまりない私には居辛いので・・・)でも、失業保険がおりないのであればそれは困ります。
また、やめても失業保険給付の3ヵ月後までに仕事が見つかれば給付の対象にはなりませんよね?だったら、2月末でやめてもそれまでに仕事を見つければいいだけなのかな、と思ったんですが・・・。
ただ、自分は営業をやっていますが結婚したら正社員でなくても契約社員や派遣で事務などで良いと思っています。しかし新卒で営業をしてきた私だと事務での再就職は難しいですかね。。。
(正社員でなくてもいいのは、結婚後できれば早いうちに子供がほしいと思っているからです)
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
6月に結婚するにあたって、先日3月末で退職したい旨上司に告げました。すると昨日、2月から会社は新しい体制に入るからできれば3月中にやめてほしいといわれました。
まだ新卒で入社して1年目です。1年働いたら失業保険はもらえると思うんですが、この場合1年未満になってしまうので失業保険給付の対象にはならなくなってしまいますか?
自分としてはやめたかった会社なので、結婚というやめる機会ができたことで良かったんですが、(実際3月末までいるのは、もう仕事のあまりない私には居辛いので・・・)でも、失業保険がおりないのであればそれは困ります。
また、やめても失業保険給付の3ヵ月後までに仕事が見つかれば給付の対象にはなりませんよね?だったら、2月末でやめてもそれまでに仕事を見つければいいだけなのかな、と思ったんですが・・・。
ただ、自分は営業をやっていますが結婚したら正社員でなくても契約社員や派遣で事務などで良いと思っています。しかし新卒で営業をしてきた私だと事務での再就職は難しいですかね。。。
(正社員でなくてもいいのは、結婚後できれば早いうちに子供がほしいと思っているからです)
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
失業保険は、半年以上勤務していれば(雇用保険に加入していれば)、受給資格があるので1年勤めたのならば
大丈夫ですよ☆
>また、やめても失業保険給付の3ヵ月後までに仕事が見つかれば給付の対象にはなりませんよね?だったら、2月末で>やめてもそれまでに仕事を見つければいいだけなのかな、と思ったんですが・・・。
この意味が、申し訳ないのですがきちんと理解出来なかったのですが・・・
失業保険は、自己都合(今回の質問者様の退職理由は自己都合となります。)での退職の場合は、
待機期間(約4ヶ月間)があり、その後に給付がはじまりますので、
待機期間にお仕事が決まってしまえば、待機期間終了後には、就職が決まっている訳ですので、
失業保険は入ってこないと思います。
ただ、これは正確にはわからないのでもしかしたらなのですが、
失業後に失業保険を申請して、ある一定期間内に再就職が決まると、
「就職祝い金」といったお金がもらえます。
これが、待機期間に仕事が決まった人にももらえるのかはわかりませんが・・・
また、次もお仕事を探される様なので問題はないかと思いますが、
例えば結婚を機に家庭に入るので仕事を探す気がないとすると失業保険はもらえませんので、ご注意下さい。
また、事務職を希望されていて、未経験で就職にあるつけるか不安なのであれば・・・保険として
失業保険はきちんと申請しておいて損はないと思いますよ。
例えば、再就職してはみたけれども、合わない・・・とすぐ辞めてしまったとしたら、それをハローワークに伝えれば
再度失業保険の受給対象になります。
事務職は派遣ですと、ほとんどの所は経験者を募集しています。
最近はそれが強い傾向にあります。
パソコンやエクセル・ワードに関しては問題なくできますか?
これが出来ないのであれば、派遣はかなり難しいですし、それでも応募出来る仕事があったとしても
アルバイトなみに時給が安い派遣だったりします。
今後、お子様を持っても、じれは少しでも働きたいと思っているのであれば、事務よりも経理の資格をとって、
経理の実務経験を積む事を考えて働いて行った方が、ゆくゆくお子様が少しでも手が離れて、働きに行きたい時に、
結構融通のきく仕事が多いようです。
例えば、月末月初の5日間だけの勤務や、1日4時間の勤務を週3回など・・・
でも、経理も派遣では未経験では難しく・・・経理に関しては事務以上に事務経験+簿記2級など求められる資格が多いのでいますぐには無理でしょうが・・・アルバイトでも経理経験をつませてくれる会社があったら、
ちょっと視野にいれると将来約にたつ可能性は事務よりあると思いますよ☆
大丈夫ですよ☆
>また、やめても失業保険給付の3ヵ月後までに仕事が見つかれば給付の対象にはなりませんよね?だったら、2月末で>やめてもそれまでに仕事を見つければいいだけなのかな、と思ったんですが・・・。
この意味が、申し訳ないのですがきちんと理解出来なかったのですが・・・
失業保険は、自己都合(今回の質問者様の退職理由は自己都合となります。)での退職の場合は、
待機期間(約4ヶ月間)があり、その後に給付がはじまりますので、
待機期間にお仕事が決まってしまえば、待機期間終了後には、就職が決まっている訳ですので、
失業保険は入ってこないと思います。
ただ、これは正確にはわからないのでもしかしたらなのですが、
失業後に失業保険を申請して、ある一定期間内に再就職が決まると、
「就職祝い金」といったお金がもらえます。
これが、待機期間に仕事が決まった人にももらえるのかはわかりませんが・・・
また、次もお仕事を探される様なので問題はないかと思いますが、
例えば結婚を機に家庭に入るので仕事を探す気がないとすると失業保険はもらえませんので、ご注意下さい。
また、事務職を希望されていて、未経験で就職にあるつけるか不安なのであれば・・・保険として
失業保険はきちんと申請しておいて損はないと思いますよ。
例えば、再就職してはみたけれども、合わない・・・とすぐ辞めてしまったとしたら、それをハローワークに伝えれば
再度失業保険の受給対象になります。
事務職は派遣ですと、ほとんどの所は経験者を募集しています。
最近はそれが強い傾向にあります。
パソコンやエクセル・ワードに関しては問題なくできますか?
これが出来ないのであれば、派遣はかなり難しいですし、それでも応募出来る仕事があったとしても
アルバイトなみに時給が安い派遣だったりします。
今後、お子様を持っても、じれは少しでも働きたいと思っているのであれば、事務よりも経理の資格をとって、
経理の実務経験を積む事を考えて働いて行った方が、ゆくゆくお子様が少しでも手が離れて、働きに行きたい時に、
結構融通のきく仕事が多いようです。
例えば、月末月初の5日間だけの勤務や、1日4時間の勤務を週3回など・・・
でも、経理も派遣では未経験では難しく・・・経理に関しては事務以上に事務経験+簿記2級など求められる資格が多いのでいますぐには無理でしょうが・・・アルバイトでも経理経験をつませてくれる会社があったら、
ちょっと視野にいれると将来約にたつ可能性は事務よりあると思いますよ☆
失業保険について。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
地方から東京か千葉に引越しをしようと思っています。
現在の仕事が契約が切れるので引越し先で失業保険を貰うのは可能なのでしょうか?
それとも現在の住居の場所でないと手続き等できずに貰えないのでしょうか?
引越してもすぐに仕事が見つかるとも限らないので、できれば探しながら失業保険がでればなと思いまして・・・
詳しい方よろしくお願いします。
ハローワークで手続きをした後に転居をした場合は、新しい住所を届け出なければならないので、手続き前でも手続き後でも、転居先で受給することは可能です。
転居先の住民票を提出すれば手続きできますが、どうもハローワークという所は、それぞれ見解が違っていたり、手続きも統一されていないようですので、事前に転居先のハローワークで住所変更の手続きに必要な書類がなんであるか聞いた方が良いと思います。
私が通っているところはとても寛容で、無知だった私は受給期間延長と言うものを知らずに出かけて行ったのですが、診断書もなしに延長手続きしてくれました。
不思議なところです、ハローワーク。
ですので、ここで質問するよりも、ハローワークに問い合わせるのが一番確実です。
転居先の住民票を提出すれば手続きできますが、どうもハローワークという所は、それぞれ見解が違っていたり、手続きも統一されていないようですので、事前に転居先のハローワークで住所変更の手続きに必要な書類がなんであるか聞いた方が良いと思います。
私が通っているところはとても寛容で、無知だった私は受給期間延長と言うものを知らずに出かけて行ったのですが、診断書もなしに延長手続きしてくれました。
不思議なところです、ハローワーク。
ですので、ここで質問するよりも、ハローワークに問い合わせるのが一番確実です。
医療費控除について教えてください。
昨年は勤めていた会社を2月に退職し、9月から別の会社でパートで働いています。
給与所得は60万円ほど、かかった医療費が6万円ほど。
この額なら還
付金があると思うのですが、失業保険20万と早期就職をしたのでその手当てが60万ほど。
失業保険は非課税と聞いたのですが、早期就職手当てが高額なのでこの場合はどのように計算すればよいのでしょう?
教えてください。
昨年は勤めていた会社を2月に退職し、9月から別の会社でパートで働いています。
給与所得は60万円ほど、かかった医療費が6万円ほど。
この額なら還
付金があると思うのですが、失業保険20万と早期就職をしたのでその手当てが60万ほど。
失業保険は非課税と聞いたのですが、早期就職手当てが高額なのでこの場合はどのように計算すればよいのでしょう?
教えてください。
早期就業支援金 ですか? ハロワで申請してもらったお金ですよね。
非課税です。
所得が60万 給与収入で125万 ならば、 5%を超えた分が医療費控除の
対象なので、3万くらい控除されます。
非課税です。
所得が60万 給与収入で125万 ならば、 5%を超えた分が医療費控除の
対象なので、3万くらい控除されます。
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
国民保険について教えてください。
先月で仕事を辞め、現在無職です。失業保険をもらうため旦那の扶養に入らず健康保険にも入れていません。(扶養に入る為には失業保険を破棄しないといけない
ため)
そこで国民保険に入ろうと思うのですが月いくらくらいになるのでしょうか?葛飾区在住です。
また支払いは加入した月から開始するのか、それとも来月から加入しようとも仕事を辞めた後から遡って支払うのかどちらでしょうか?
明日加入したとしたら今月はあと3日の為に1月分も払うのなら2月になってから加入したいと思ってます。
来月には病院に行く用事がありそうなので早々に入りたいと思っています。
よろしくお願いします。
先月で仕事を辞め、現在無職です。失業保険をもらうため旦那の扶養に入らず健康保険にも入れていません。(扶養に入る為には失業保険を破棄しないといけない
ため)
そこで国民保険に入ろうと思うのですが月いくらくらいになるのでしょうか?葛飾区在住です。
また支払いは加入した月から開始するのか、それとも来月から加入しようとも仕事を辞めた後から遡って支払うのかどちらでしょうか?
明日加入したとしたら今月はあと3日の為に1月分も払うのなら2月になってから加入したいと思ってます。
来月には病院に行く用事がありそうなので早々に入りたいと思っています。
よろしくお願いします。
国保の手続きには離職票が必要です。
もし1月30日退社になっているなら1月分から国保料が発生します。
★★★
それならば1月から国保です。2月に申請しても1月から保険料が発生します。
もし1月30日退社になっているなら1月分から国保料が発生します。
★★★
それならば1月から国保です。2月に申請しても1月から保険料が発生します。
結婚退職に伴う失業保険
結婚をして、現在の住まいから新幹線で6時間ぐらいかかる場所に引っ越す予定です。
この場合、待機期間をまたずに、すぐに失業保険は給付されますか?
結婚をして、現在の住まいから新幹線で6時間ぐらいかかる場所に引っ越す予定です。
この場合、待機期間をまたずに、すぐに失業保険は給付されますか?
〉待機期間
「給付制限」ですね。
退職から引っ越しまでの期間が概ね1ヶ月以内、という条件もありますよ。
また、結婚・引っ越しをして初めて条件を満たします。
「給付制限」ですね。
退職から引っ越しまでの期間が概ね1ヶ月以内、という条件もありますよ。
また、結婚・引っ越しをして初めて条件を満たします。
関連する情報